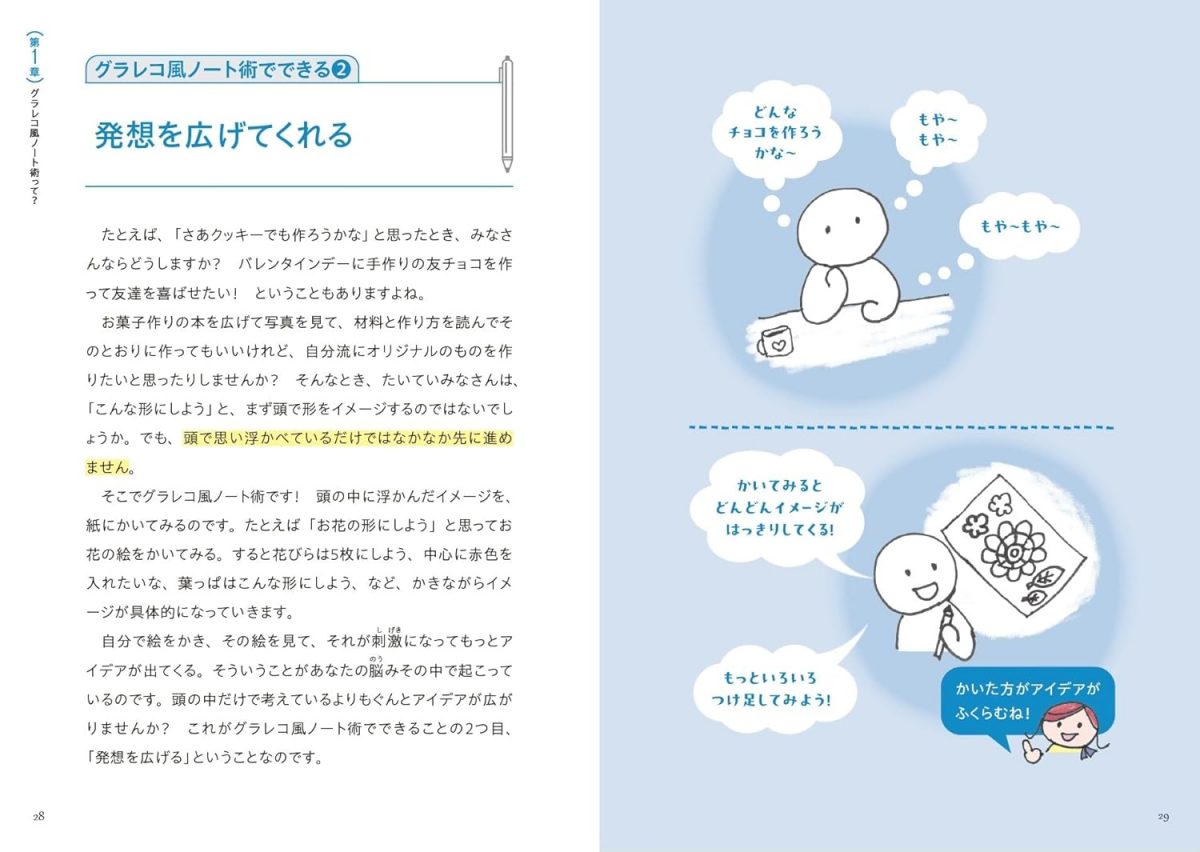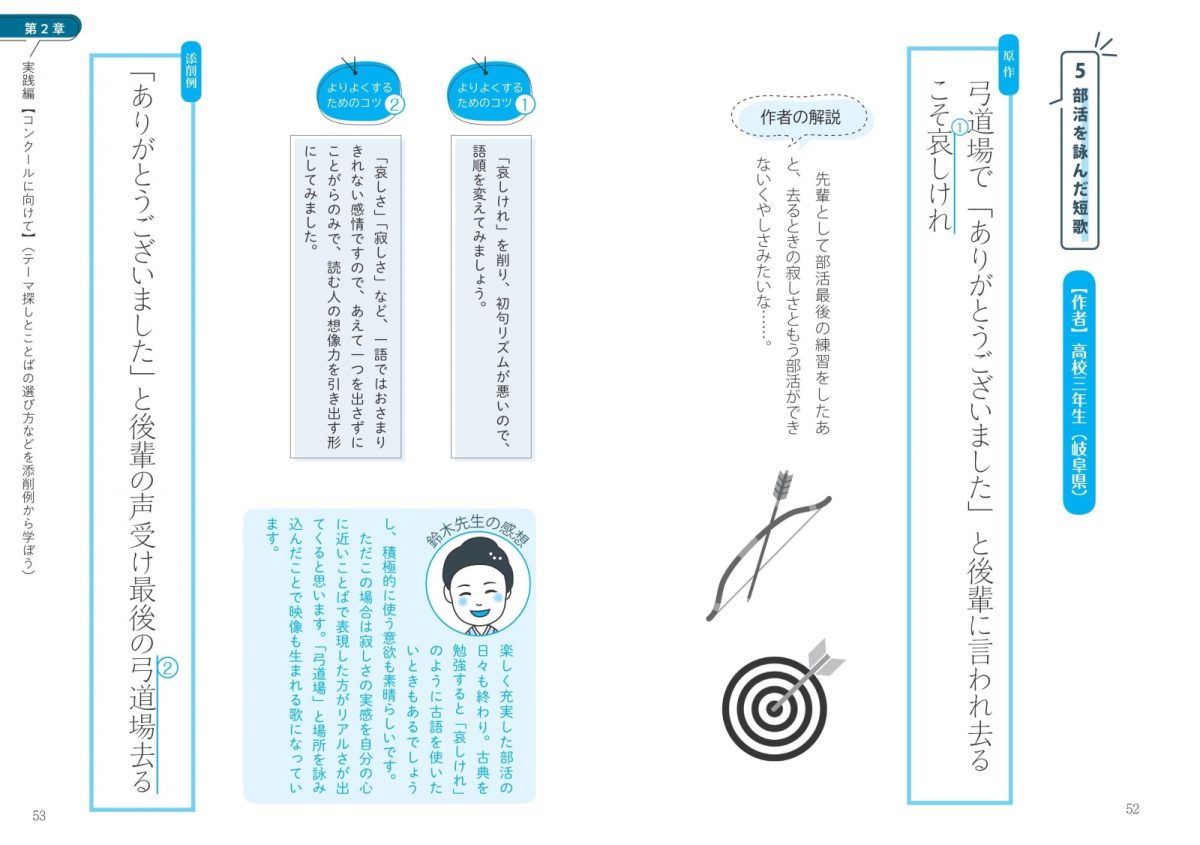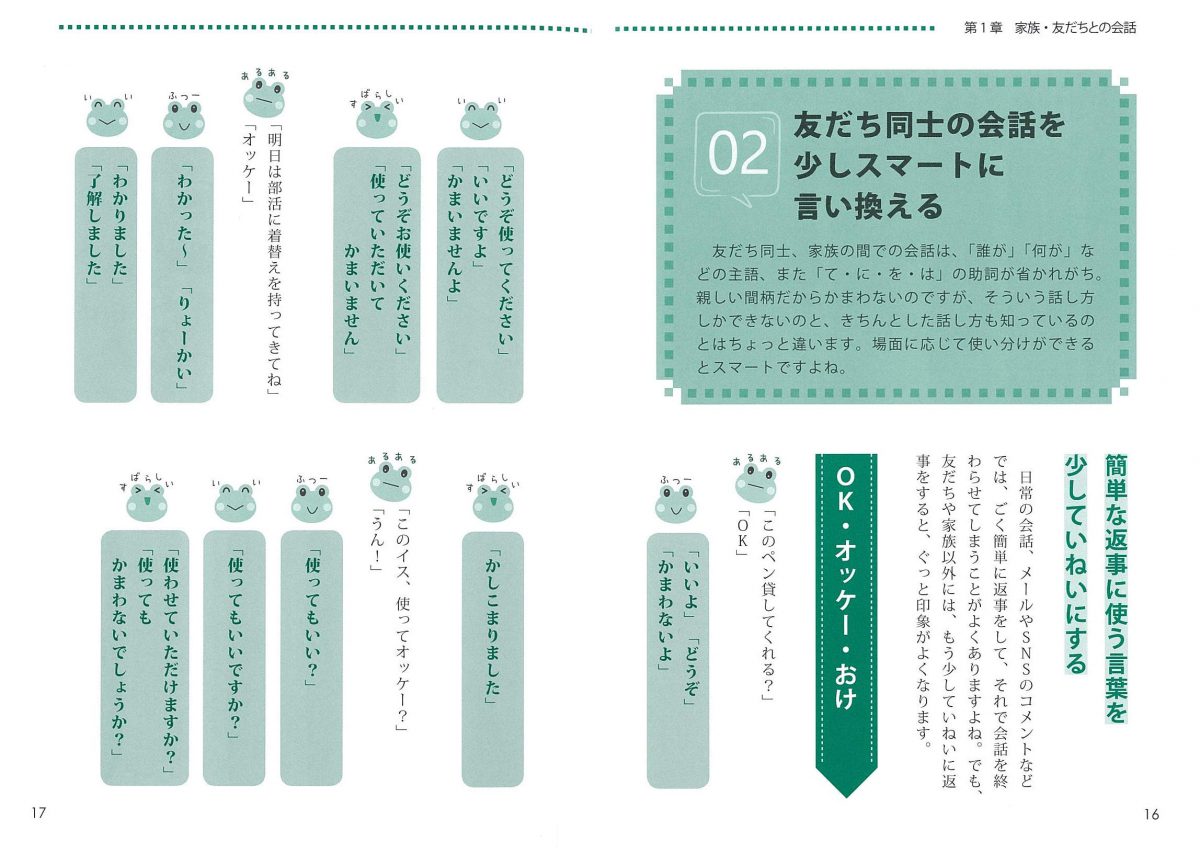図と絵で整理しひらめきを生む 13歳からのグラレコ 学びを楽しむノート術
12月 25th, 2024 Posted in コツがわかる本, ジュニア, 中学生向け, 学習 | 図と絵で整理しひらめきを生む 13歳からのグラレコ 学びを楽しむノート術 はコメントを受け付けていません
★ ノートを使って『学びを自分の力』にする!
★ グラレコ=グラフィックレコーディングとは?
絵や図を使った視覚的でわかりやすい記録法
★ グラレコをもっと簡単に!
★ 絵が上手くなくてもペン1本で始められる
「グラレコ風ノート術」
*わかりやすく、記憶に残りやすく、
アイデアが広がる
*情報の整理・発送・共有が上手くなる
★ 授業のノートのほか、日記やスケジュール帳、
話し合いの記録などにも
◇◆◇ 本書について ◇◆◇
コクヨで働き、仕事を通じて子どもから大人まで
1000名を超えるさまざまな人びととの
傾聴と対話の経験から絵の力のすごさを実感した
「普通のワーカー」である著者が、
長年の実体験と思考を繰り返す中で
編み出してきた知恵の集大成
「グラレコ風ノート術」
学びが深まり発想が生まれるから、
学校生活での勉強や記録だけでなく、
大人になっても役立つ、一生使える!
◇◆◇ 著者からのコメント ◇◆◇
この本では、絵や図を使って、
ノートをグラフィックレコーディング
(グラレコ)風にまとめる方法
(グラレコ風ノート術™)をお伝えします。
グラレコ風ノート術™を活用すると、
ふだんの学習がわかりやすく楽しくなりますし、
言いたいことが人に伝わりやすくなります。
ノートにかいた情報をもとにアイデアを広げたり、
発展させたりすることもできます。
大人になってもいろいろ役立ちますよ。
グラレコ風ノート術™は、
知識をまとめたり、何かを人に伝えたり、
むずかしい話をわかりやすくしたりするときに、
とても便利だということ、
そしてその力は社会人になっても
役立つということです。
ぜひ、みなさんもグラレコ風ノート術™に
挑戦してみてくださいね。
樋口 美由紀
◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇
☆第1章 グラレコ風ノート術って?
* グラレコ風ノート術とは?
* グラレコ風ノート術ができると授業の
ノートが変わる!
* グラレコ風ノート術のメリット
・ペン一本で簡単に始められる
・絵が上手でなくてもいい
・・・など
☆第2章 とにかくやってみよう
* 考えるより手を動かそう
* 必要な道具はこれだけ!
* 基本イラストをかいてみよう
* 人をかいてみよう
* 身の回りのものをかいてみよう
・・・など
☆第3章 目的別グラレコ活用法
* グラレコ風ノート術が活躍する3つの場面
* 情報を集めて整理する
・確かな情報か、新鮮な情報か?
* 聴きながらメモする
* アイデアを広げる
・整理したノートから発想する
・・・など
☆第4章 学んだことを今日から使ってみよう
* ふだんのメモに使ってみる
* 日記をグラレコ風にかいてみる
* スケジュール帳をグラレコしてみよう
* ネタ帳を持ち歩こう
・・・など
☆第5章 グラレコ風ノート術を話し合いにも使ってみよう
* 話し合いの内容をその場で形にしていこう
* ホワイトボードにかいてみよう
・・・など
☆第6章 授業でも使ってみよう
* 英語編 覚えづらいことはビジュアルで理解しよう
* 国語編 情景が目に浮かぶようにイラスト化しよう
・・・など
☆ 応用編 いろいろな場面でグラレコ風ノート術を使ってみよう!
* パーツを組み合わせて表現の幅を広げよう!
* 4コママンガでストーリーをまとめよう!










 コツがわかる本
コツがわかる本 マミーズブック
マミーズブック まなぶっく
まなぶっく パパ・ママ教えて
パパ・ママ教えて わかる本
わかる本