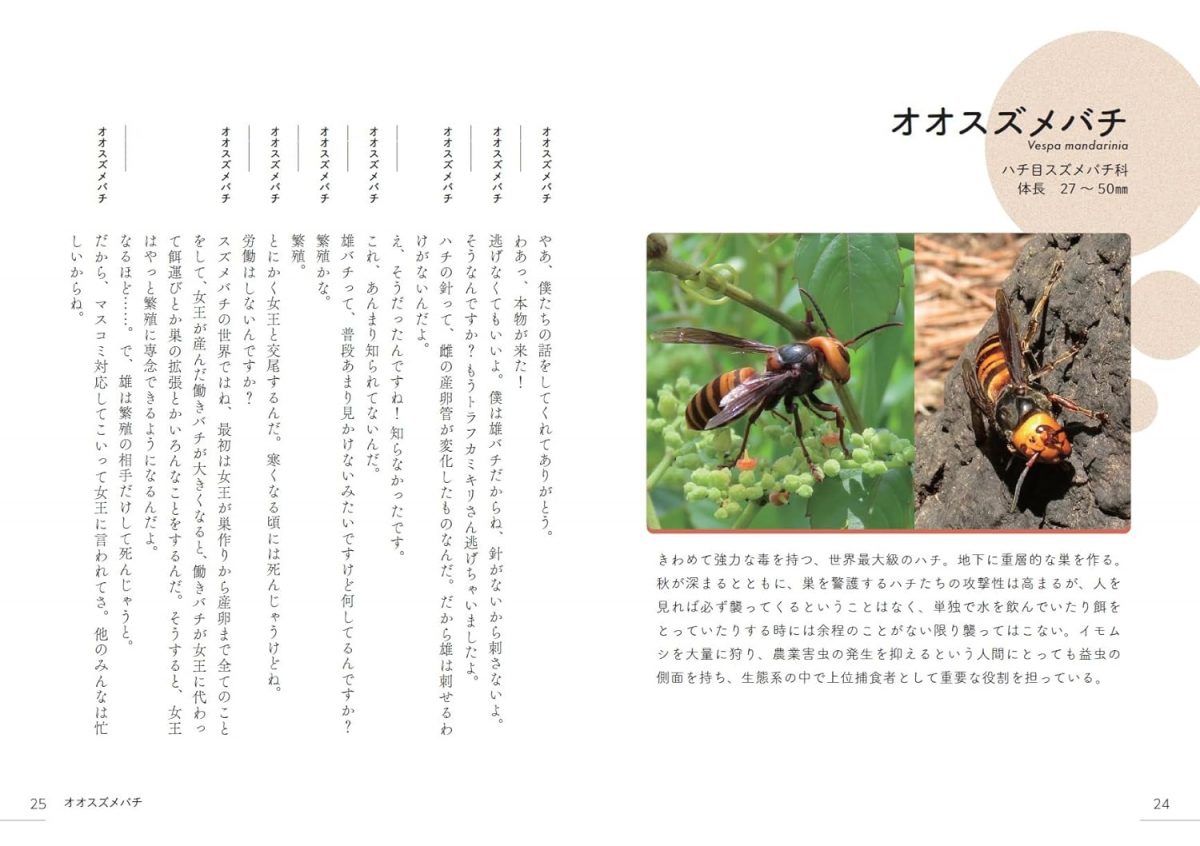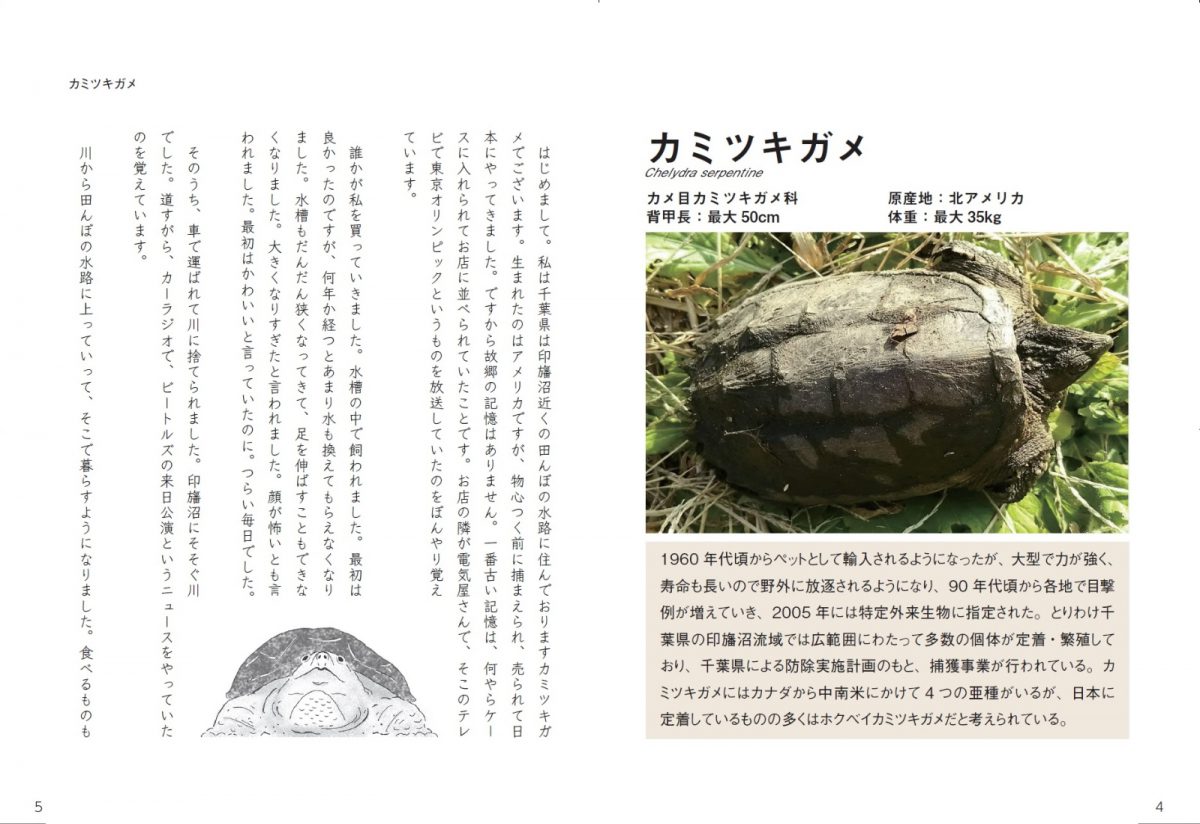みんなが知りたい! 深海のひみつ 奇妙な生物たちがすむ 暗闇の世界と調査の歴史
7月 31st, 2025 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, ホーム最新刊, 児童, 学習読み物 | みんなが知りたい! 深海のひみつ 奇妙な生物たちがすむ 暗闇の世界と調査の歴史 はコメントを受け付けていません★ 調べ学習に役立つ!
★ 写真や図解でやさしく解説
*へんてこ、透明、光、超巨大…
深海でくらすために工夫をこらした生物たち
*研究者のひとはどうやって深海を
調査するの?
どうやってもぐるの?
*海にも山があるって、どういうこと?
深海には、地上では見られないような
不思議なすがたをした生き物が
さまざまにくらしています。
不思議なすがたをしているわけは、
深海の環境にひみつがあります。
長い時間をかけて調査して、
そのひみつが少しずつ
解明されてきました。
でも、わからないことが
まだまだたくさんあります。
深海は人間にとって
未知の世界でもあるのです。
◇◆◇ 監修者からのコメント ◇◆◇
みなさんは、深海ってどんなところだと思いますか?
真っ暗で、冷たくて、すさまじい水圧がかかるから、
人間はほんの少しの時間もいられない
過酷な環境です。
そんな深海には、びっくりするほど
面白い生きものたちがくらしています。
光でえさをおびき寄せるチョウチンアンコウ。
アゴを発射して獲物をとらえるミツクリザメ。
死んだクジラの骨の栄養を
吸いとって生きるホネクイハナムシなど。
ヘンテコな生きものたちは、実は生きるために
すごい能力をもった「強者」ばかり。
深海生物からしたら人間の方が
「ヘンテコ」に見えるかもしれないですね。
もし、深海に行けるとしたら、
真っ暗でちょっぴり怖い!
けれど、まだ誰も見たことがない
ヘンテコな生きものや美しい景色に
であえるかもしれません。
深海には、まだたくさんのひみつが隠されています。
この本を読んで、
「深海をもっと知りたい!」と思ってもらえたら、
とってもうれしいです。
みんなが知りたい! 深海のひみつ編集部
◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇
☆第1章 深海生物とのであい
* 深海生物の驚くべき能力
* ヘンテコな生きもの
* 暗闇の戦略家
* 深海のトップ・プレデター
* 超深海で発見された生きもの
・・・など
☆第2章 深海ってどんなところ?
* 深海の世界をイメージしよう
* 深海の地形を見てみよう
* 世界で一番深い谷
* 世界で一番高い山
* 日本は深海大国
・・・など
☆第3章 深海に探索へ!
* 研究者を深海へ連れていく「しんかい6500」
*「しんかい6500」を大解剖!
* 深海調査のため「よこすか」が出航!
* いよいよ深海へ!
*「しんかい6500」のパイロットの仕事とは?
・・・など










 コツがわかる本
コツがわかる本 マミーズブック
マミーズブック まなぶっく
まなぶっく パパ・ママ教えて
パパ・ママ教えて わかる本
わかる本